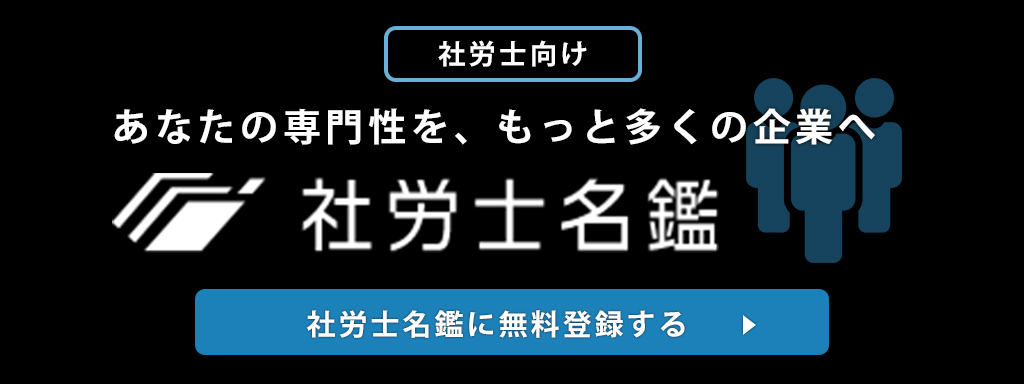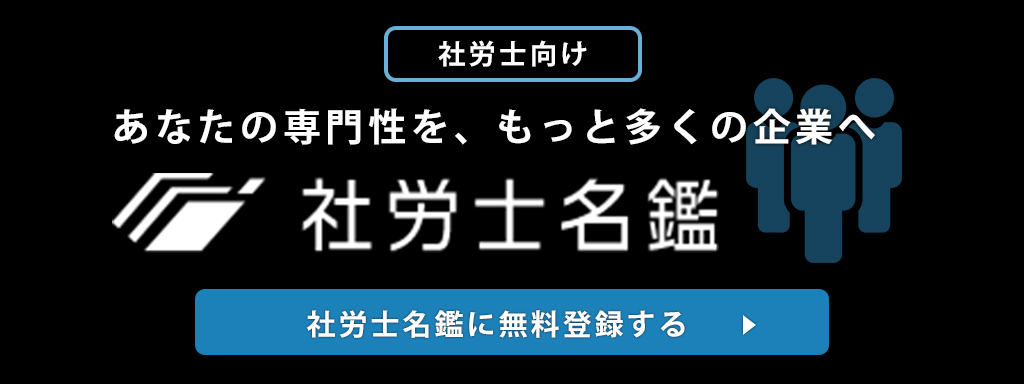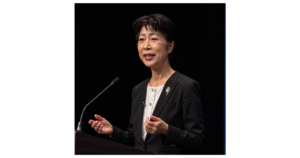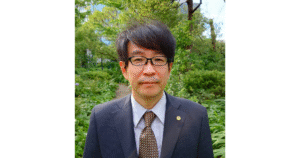今回インタビューをさせていただいたのは、社会保険労務士、みなとみらい人事コンサルティング代表の泉 文美さんです。
長年、派遣元・派遣先・職業紹介責任者講習主任講師を務められており、顧問先も95%が派遣・紹介会社という、人材派遣・紹介業界に精通されている社労士さんです。
プロフィール

| 名前 | 泉 文美 |
| 事務所名 | 社会保険労務士みなとみらい人事コンサルティング |
| 生年月日 | 1980年5年26日 |
| 出身地 | 横浜 |
| 社労士歴 | 13年(2012年6月開業) |
| 趣味 | 読書(特に歴史関係)、芸術鑑賞 |
| 尊敬する人物 | 毛利元就(戦国武将) |
| HP | https://mmjinji.com/ |
特徴
- 派遣元責任者講習主任講師。顧問先の95%が派遣会社。
- 複雑で繊細な問題も、小中学生が理解できるレベルで徹底解説
- ゼロキャリアから、数少ない東大卒の女性社労士へ!
対応業務
- 人事・労務コンサルティング
- 給与計算・保険手続き
- 就業規則・人事評価制度
- 助成金申請
- 人材ビジネス(派遣・紹介)
- 人材採用・育成・定着
得意な業種
- 人材派遣会社
- 人材紹介会社
これまでのキャリアについて
 編集部
編集部社労士になるまでのキャリアについて教えてください。
泉さん:大学卒業してから社労士になるまで、はっきりとしたキャリアというのは実はないんです。
2つ年上の夫とは、大学在学中から交際していて、彼は当時すでに自動車関連の商社への就職が決まっていました。その会社は全国転勤はもちろん海外駐在の可能性もある企業だったため、私が東京で就職してしまうと別居婚になってしまう状況でした。そのため、私の卒業式の当日に入籍をし、その1週間後にはもう夫の最初の赴任地である茨城県ひたちなか市へ引っ越しました。それからも夫の転勤に伴って、全国様々な場所へ移り住む生活が始まったのです。途中夫が3ヶ月間アメリカへ行くといったこともあり、引っ越しばかりの日々はかなり大変でした。
もちろんこの状況下では、定職に就くどころか、パートで働くことも難しく、レギュラーの仕事はできません。その代わりに、引っ越す先々で単発のアルバイトをしていました。例えば、宇都宮にいた際には、東武百貨店で開催された北海道物産展で10日間だけ働く、そのようなイメージの生活でしたね。



そのような日常が変化したのには、何かきっかけがあったのですか?
泉さん:夫の転職がきっかけで、いつもより長めに定住できる時があったんです。その時は愛知県だったんですけど、もしかしたらここでならレギュラーのバイトができるかもしれないと思って、本屋さんでアルバイトを始めました。
これまで色んな場所を転々としていた時に、アルバイト仲間から何度か言われていたことがあって、「泉さん、この歳になるとね、アルバイトもなくなるよ」って。その方は60代くらいの方だったんですが、それを聞いて、「私も何か手に職をつけないと」と思い始めていたんです。
そういった経緯から自分のこれまでを振り返ると、私には正社員経験がないことに改めて気づきました。私のような人間は、資格があった方がいいかもしれない。そう思い、当時働いていた本屋さんで資格について調べてみました。そこで社会保険労務士という資格を知りました。
数ある資格の中でも社会保険労務士に興味を持ったのは、それまでの生活が大きく影響しています。夫が初めて転職した際、ハローワークに離職票を持っていけば失業給付がもらえることすら、当時は知らなかったんです。後からそのことを知り、自分の世間知らずを痛感しましたし、こういう知識を持っていれば人生にプラスになるんだなと感じていました。こうした経験から、社会保険労務士という仕事が自分にとって一番身近に感じられたのです。
また、社労士は合格者の約4割が女性であることも、この資格を目指すきっかけの一つになっています。



キャリアが0の状態から、社会保険労務士の資格を取って、独立までされるのはとても大変だったのではないでしょうか?
泉さん:社労士の資格取得を決意してからは、自宅学習と実務経験を両立させました。
学習面では、引っ越しの可能性があったため、勉強は通信講座を選択しました。大学受験も通信教育で乗り切ったほど、自宅学習が好きだったんです。
実務面でも経験を積むため、社労士関連のアルバイトに絞って仕事を探しました。
まず愛知県豊橋市にある社会保険事務所(現:年金事務所)で、臨時職員として年金業務の手伝いをしました。役所の窓口業務は非常勤職員が担当することが多いので、正社員経験がなくても「社労士の勉強をしています」とアピールし、採用してもらえたんです。
4ヶ月の勤務を終えた後、ハローワークで仕事を探していたところ、「ちょうどこのハローワークで人を募集しているんだけど」と声をかけられました。当時、リーマンショックで失業者が急増し、非常勤職員を増やす必要があったそうです。そこは愛知県蒲郡市にある小さなハローワークだったので、担当部署はなく、求人や失業給付の相談、助成金の受付など、非常勤も全員で、あらゆる業務に対応していました。さらに、当時の所長のご厚意で、昼休みの時間などに会議室で資格勉強をさせてもらったりもしていました。おかげで社労士試験の雇用保険の分野は満点で合格することができ、ハローワークの所長には感謝を伝えに行きました。
その後、夫の転勤で関東へ引っ越すことになったのですが、ちょうど、神奈川県厚木市にあるハローワークの求人受付部署で臨時職員の求人が出ていたので、応募したところ、蒲郡のハローワークの所長が厚木のハローワークに紹介状を書いてくださって、無事採用され、関東でも引き続き実務経験を積むことができました。
多くの方々の温かい応援に支えられ、資格取得・開業に向けた準備期間を乗り越えることができました。
社会保険労務士みなとみらい人事コンサルティングの特徴



社会保険労務士みなとみらい人事コンサルティングさんの特徴を教えてください。
泉さん:当事務所の顧問契約先の95%が人材派遣・紹介会社です。人材派遣・紹介会社の企業様から多く仕事をいただいているのは、開業当初から厚生労働省指定の派遣元・派遣先・職業紹介責任者講習の委託を受けて、講師をしているおかげだと考えています。
これまで担当した講習は通算150回以上で、延べ3000人以上の方が受講されています。受講者に対して行なっているアンケートでは、満足度平均93%を獲得しており、好評をいただいています。
この講習は、単に私が知識を伝えるだけでなく、人材派遣・紹介業界の現場で働く方々から実情を教わることで、法律の知識と現場の感覚、その両方を身につけることに役立っていると感じています。
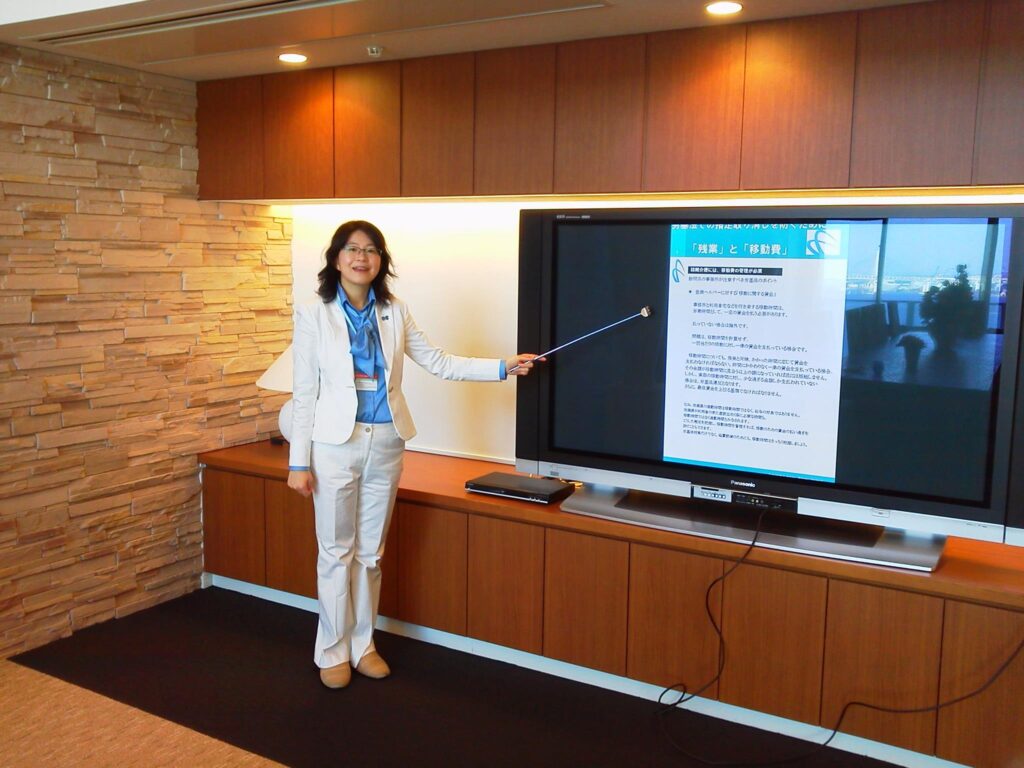
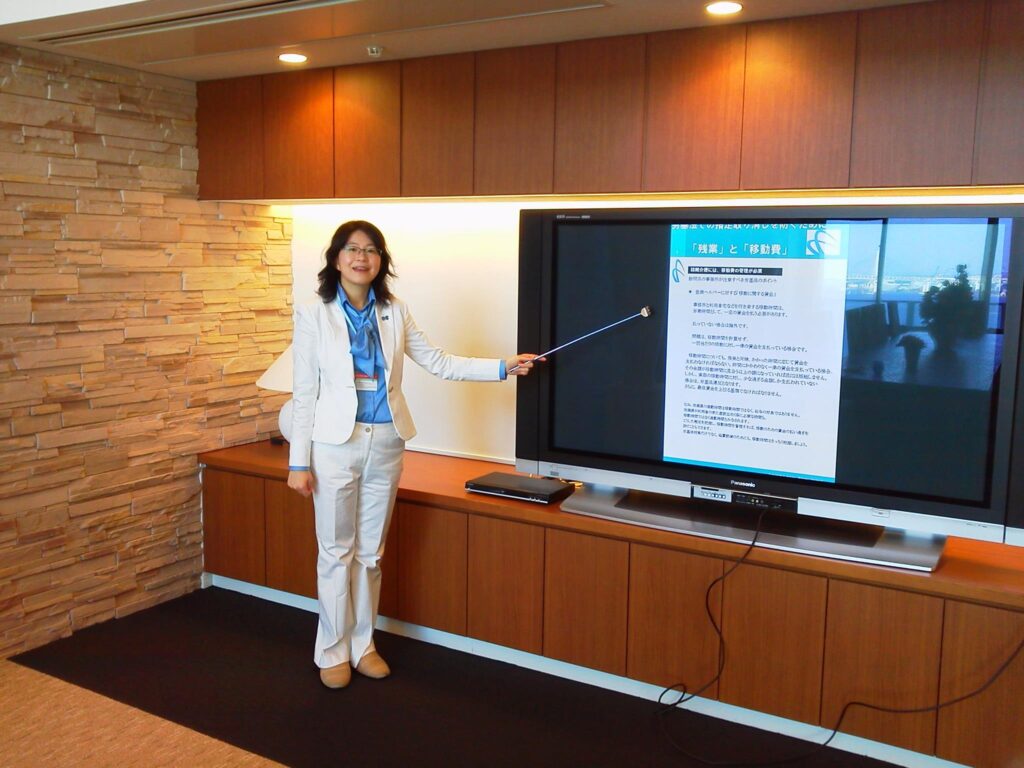
また、派遣・紹介会社に対して数年に一度定期的に入る労働局の調査にも、当事務所はしっかり対応いたします。多くの社労士がこの対応を避けたがりますが、私はそうした調査の矢面に立ち、お客様のために全力を尽くします。
他にも、お客様のために、派遣先や紹介先の企業に一緒に行って頭を下げて派遣料金の値上げをお願いしたり、交渉の場に同席したり、お願いの手紙を書いたりすることもいとわない姿勢で臨んでいます。こうしたスタンスから、セカンド顧問としてご依頼いただくケースも非常に多くなりました。「給与計算や社会保険手続きはメイン社労士に任せているけれど、派遣・紹介のことだけは泉さんにやってほしい」といったご依頼も大歓迎です。
お仕事をする上で大切にしていること



お仕事をされるうえで大切にされていることを教えてください。
泉さん:私は常々「社労士界の池上彰さん」を目指しています。専門用語を並べ立てて難しく話すような社労士なら、必要ないと考えているからです。複雑で繊細な法律に関する内容も、中学生や小学生でもわかるような言葉に置き換えて、お客様が理解できる説明にすることを心がけています。大学卒業後、百貨店の物産展などで単発のアルバイトをしていた経験から、「お客様は神様」という考え方が身に付いていることも影響していると思います。私はこういう職業ですから、お客様に先生と呼んでいただける立場にはありますけれども、偉そうにするつもりはありません。お客様が「はあ……」と戸惑うような難しい説明をするのではなく、私の知識を最大限に活用し、お客様にわかりやすく伝えることが私の使命だと考えています。


読者の皆さまへメッセージ



読者の皆さまへメッセージをお願いします。
泉さん:当事務所は2012年の開業当初から、一貫して派遣会社や職業紹介会社のサポートを続けてきました。現在、当事務所の顧問先の95%以上が派遣・紹介関連の企業様です。
今も厚生労働省の委託を受けて派遣元・派遣先・職業紹介責任者講習の講師を続けています。このため、法律の知識と現場の実務、その両方を深く理解していることが私の強みです。
講習ばかりに専念し派遣・紹介会社の顧問先を持っていない社労士や、人材派遣・紹介業界出身を売りに開業していても、自分が業界にいたころの、古い知識のままで止まっている社労士もいる中で、私は文字通り「派遣・紹介にどっぷり」と浸かっています。ここまで派遣・紹介に特化している社労士は、日本でもなかなかいないと自負しています。
派遣会社様、職業紹介会社様、そして派遣労働者を受け入れる派遣先の皆様。「人材派遣・紹介業界」という複雑な分野でお悩みでしたら、ぜひ「餅は餅屋」で人材派遣・紹介業界に特化した当事務所にお気軽にご連絡ください。